個人再生での生命保険の扱い|清算価値に計上されるか
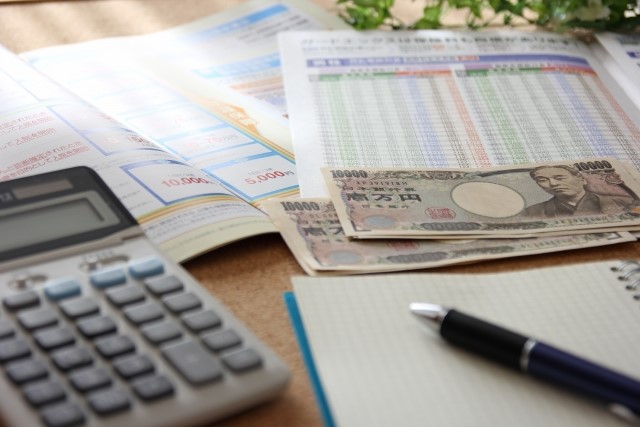
個人再生手続は、支払いきれなくなってしまった借金を、減額して分割払いすることを裁判所に認めてもらい、その返済を終えると借金が免除される債務整理手続が個人再生です。
自己破産のように高額の財産が処分されることはありませんが、自己破産で債権者に配当される金額以上を支払わなければなりません。
退職金等とともに生命保険の解約返戻金は、債務者の財産とされるため、個人再生により返済する金額に影響を与えます。
他にも契約者貸付制度を利用している場合などの処理も問題になります。
ここでは、個人再生での生命保険の扱いについて説明します。
このコラムの目次
1.個人再生について
(1) 個人再生手続の概要―自己破産との違い―
個人再生は、支払不能となった債務者が、最低限支払わなければならない金額の借金について、原則3年(最長5年)の分割払いをする計画である再生計画案を裁判所に提出し、裁判所が再生計画認可決定をすれば、債務者は計画に従った返済を終えることで、残る借金を免除してもらえる債務整理手続です。
自己破産と違って、借金は完全には無くならず、計画に基づく返済が必要ですが、自己破産では没収されてしまう高額な財産を維持することが出来ます。
例えば、住宅ローンが残っている住宅のような不動産等です。
(2) 最低限支払うべき金額の定め―最低弁済額と清算価値の大きい方―
再生計画で最低限支払わなければならない金額は、個人再生をするために用いる手続の種類にもよるのですが、一般的には、法律が定める最低弁済額か、清算価値のいずれか大きい方になります。
最低弁済額は、借金総額に応じて定められています。目安としては、借金総額の5分の1程度となることが多いです。
清算価値とは、仮に債務者が自己破産した場合に債権者が債務者の資産から受け取ることのできると見込まれる金額のことを言います。
債務者の生命保険が影響を与えるのは、この支払額の基準である清算価値なのです。
2.清算価値保証の原則と生命保険の解約返戻金
(1) 清算価値保証の原則
個人再生では、基本、高額な財産を失うことはありません。
しかし、債務者の財産から配当を受け取ることが出来ない債権者のために、債務者が自己破産した場合に債権者に配当される債務者の財産、つまり清算価値相当額については、最低限支払わなければなりません。
これを、清算価値保証の原則と言います。
(2) 生命保険の解約返戻金について
保険金以外に保険会社からお金が支払われることのない掛捨て型の生命保険では、解約返戻金はありませんので、個人再生する上で問題にはなりません。
一方、解約すると支払期間次第でそれまで支払ってきた保険料以上のお金を受け取れる生命保険もあります。
定期預金や年金代わりに用いられることもあり、貯蓄型と呼ばれています。
そして、保険の解約により支払われるお金を解約返戻金と呼びます。
解約返戻金は、定期預金のようなものですから、債務者の財産として扱われます。そのため、清算価値に計上しなければならないのです。
(3) 生命保険の解約の必要性
個人再生では、生命保険を解約する必要は、制度上はありません。
生命保険の解約返戻金が清算価値に含まれると言っても、自己破産と違ってそれを債権者に配当するわけではありません。
解約返戻金が問題となるのは、あくまで再生計画での支払額の基準である清算価値の金額がいくらかを決めるためであり、個人再生をすると必ず生命保険を解約しなければならないわけではないのです。
ただし、解約返戻金が非常に高額となった場合は、生命保険を解約せざるを得なくなる恐れがあります。
解約返戻金を計上したせいで、清算価値の金額が、債務者の収入では支払いきれないほどに膨らんでしまった場合、そのままでは再生計画の実行可能性がないとして裁判所が再生計画を認めてくれません。
そこで、裁判所に再生計画を認めてもらえるよう、解約返戻金を取り崩して再生計画に従った返済に充てるために、生命保険を解約しなければならなくなることもあり得ます。
(4) 例外的に解約返戻金が清算価値とならない場合
自己破産の配当手続では、自由財産と呼ばれる一定の財産は債務者の生活のために残されます。
そのため、清算価値を計算する際にも、自由財産に当たる分は控除されます。
裁判所の運用によっては、解約返戻金が一定額以下であれば、自由財産に当たるとして清算価値に計上しない場合もあり得ます。
もっとも各地の裁判所により、細かな運用は違うことが多いので、必ず弁護士に確認して下さい。
3.契約者貸付を利用している場合
契約者貸付とは、解約返戻金のある生命保険の場合に、保険会社からお金をもらい、低利を付けて返還する制度です。
(1) 契約者貸付の性質
契約者貸付は、「貸付」という名前に反して、実は貸付金、つまり借金ではありません。
契約者貸付は、解約返戻金を前払いするものなのです。
解約返戻金は債務者の財産ですから、前払いとはいえ、それを債務者が受け取り利用することは自由です。
そのため、契約者貸付を受けている債務者が個人再生をする場合、解約返戻金を清算価値に計上する際に、契約者貸付の金額を解約返戻金の額から差し引くことになります。
(2) 契約者貸付に関する注意点―偏頗弁済等―
契約者貸付を利用すれば、清算価値に含まれる解約返戻金を、ひいては再生計画での支払総額を減らせると思う方もいるかもしれません。
しかし、そのようなことをすると個人再生での債務整理自体に支障が出かねません。
そもそも、契約者貸付で受け取ったお金を、現金や貯金としてそのまま持っていれば、結局、債務者の財産総額は変わりませんので、清算価値は減りません。
一方、特定の債権者への一括返済に充ててしまうと、このような返済は、債権者を不平等に扱うものだとして禁止されている偏頗弁済になってしまいかねません。
そして、偏頗弁済をすると、弁済額が清算価値に上乗せされます。
そのため、この場合も清算価値は減りません。
おとなしく生活費に充てたとしても、再生計画に従った返済が出来るだけの収入が無いのではないかという疑いを、裁判所が持ってしまう恐れがあります。
結局、契約者貸付を個人再生の手続上有効活用するとしたら、弁護士費用や裁判費用への工面程度でしょう。
返済に困ったからと言って、弁護士に確認せず、安易に契約者貸付を利用しないようにしてください。
4.契約名義人と保険料負担者が異なる場合
(1) 解約返戻金はどちらの財産となるのか
生命保険の契約名義人と、保険料負担者が異なることは、親族間などでしばしばされています。
生命保険の解約返戻金は、親から子への財産の贈与や、親が自らの年金代わりに用いることが出来るからです
では、このような場合に生命保険の解約返戻金を受け取ることが出来るのは、名義人と保険料負担者のどちらなのでしょうか。
(2) 解約返戻金が保険料負担者の財産となる場合
保険料負担者が、他人の名義を無断で借用して、自ら保険料を支払って解約返戻金も自分のものにしようとしていた場合には、保険料負担者が保険契約を締結しており、解約返戻金も名義人ではなく保険料負担者の財産ということになります。
そう言えるかは、具体的な事情をもとに裁判所が判断することになりますが、主に問題となる事情は以下の通りです。
①保険料の負担
前提として、裁判所に名義人が保険料を負担していなかったことを認めてもらわなければなりません。
保険料支払いの記録がある預金通帳などの明確な証拠がまず必要です。
保険料支払いがわかる名義人以外の者の預金通帳があったとしても、同居していて家計が同一であれば、仕送りが多すぎると、名義人が保険料を負担していたとされる恐れがあります。
②名義人が保険契約を知っていたか
具体的には、名義人が保険料の控除を受けていた場合や契約者貸し付けを利用していた場合、生命保険の存在を認識していることが明白であるため、名義人の資産となるケースが多いです。
いずれにせよ、細かい事情を積み重ねていかないと裁判所を説得できませんから、清算価値の計算やそれに基づく個人再生を含む債務整理の見通しを立てるためにも、弁護士に早くから相談しましょう。
5.個人再生のことなら泉総合法律事務所へご相談下さい
貯蓄型の生命保険は、解約返戻金があるために、再生計画での返済額に大きな影響を与える場合があります。
個人再生手続では保険を残すことはできますが、正しい知識が無いと返済額が大きく増えてしまうリスクがあります。
そのようなリスクを避けるためには専門家である弁護士へ相談するべきでしょう。
泉総合法律事務所では、これまで個人再生を含む債務整理により多数の借金問題を解決してきた豊富な実績があります。個人再生のことなら泉総合法律事務所へご相談下さい。
-
2020年3月24日債務整理 個人再生をすると車はどうなる?知っておくべき個人再生と車の関係
-
2019年1月17日債務整理 個人再生手続の注意点|家賃や水道光熱費などの支払いについて
-
2019年6月4日債務整理 自己破産後に借金を請求されたらどうすればいいか?




